マウスピース矯正中に歯ぎしりをするとどうなる?リスクと対策
こんにちは。千葉県野田市にある歯医者「R歯科・矯正歯科クリニック」です。

「マウスピース矯正中だけど睡眠中に歯ぎしりをしているらしい」「マウスピースが壊れないか心配」という不安を抱えている方は少なくありません。歯ぎしりは睡眠中に無意識で行われるため、特にマウスピース矯正中は装置と歯の両方に影響を与える可能性がありす。
この記事では、歯ぎしりの基本的な仕組みや原因、マウスピース矯正中に歯ぎしりをすると起こりうるリスク、そして日常生活でできる具体的な対策まで詳しく解説します。安心してマウスピース矯正を進められるよう、参考にしてください。
歯ぎしりとは

歯ぎしりは、睡眠中に無意識に歯と歯をこすり合わせたり、強く噛み締めたりする癖の総称です。医学的にはブラキシズムと呼ばれ、多くの方にみられる習慣の一つです。
歯ぎしりの種類
歯ぎしりには、主に3つのタイプがあります。
1つめがグラインディングで、上下の歯を強くこすり合わせるタイプの歯ぎしりです。ギリギリと音を立てることが特徴で、周囲の人が気づきやすいタイプです。歯の表面がすり減ったり、歯茎に負担がかかったりするリスクがあります。
2つ目がクレンチングで、歯を強く噛み締めるタイプの歯ぎしりです。音が出ないため、周囲の人や本人も気づきにくいのが特徴です。歯や顎関節に強い圧力がかかるため、顎の痛みや頭痛、肩こりなどを引き起こすことがあります。
3つ目がタッピングで、上下の歯をカチカチと短時間、連続してぶつけ合うタイプの歯ぎしりです。グラインディングやクレンチングに比べて、頻度は少ないとされています。
これらの歯ぎしりは、自覚がないまま行われていることが多く、歯や顎、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、マウスピース矯正中は歯に外部から力を加えているため、歯ぎしりの影響がより大きくなります。
歯ぎしりが及ぼす影響
歯ぎしりは矯正治療中の方に限らず、矯正治療をしていない方にとっても、さまざまな問題を引き起こします。ここでは、歯ぎしりが及ぼす一般的な影響について解説します。
歯のすり減り
歯ぎしりによって、歯の表面を覆うエナメル質という組織がすり減り、内部の象牙質が露出することがあります。これにより、歯がしみやすくなる知覚過敏や、虫歯になりやすい状態になることがあります。
また、強い力が加わることで歯にひびが入ったり、最悪の場合、歯が割れたりする可能性もあります。
顎や筋肉に負担がかかる
歯ぎしりは、顎関節や顎の周囲の筋肉に大きな負担をかけます。これにより、顎を開け閉めする際に音が鳴ったり、口を開けにくいといった症状を引き起こすことがあります。また、顎の筋肉が過度に発達し、エラが張ったような顔の輪郭に変化することもあります。
頭痛や肩こりにつながる
歯ぎしりによって、頭痛や肩こり、首のこりなどの症状が現れることがあります。これは、顎の筋肉が緊張することで、周囲の筋肉にも影響が及ぶためです。睡眠の質も低下し、日中の集中力の低下など、日常生活にも支障をきたすことがあります。
歯ぎしりを引き起こす主な原因

歯ぎしりの原因は一つではありません。複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
ここでは、歯ぎしりを引き起こす主な原因について詳しく見ていきましょう。
心理的な要因
歯ぎしりの原因として、最も一般的なのがストレスです。日常生活で感じる精神的なストレスや緊張、不安などが、無意識のうちに歯ぎしりとして現れることがあります。
ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になります。その結果、睡眠中も体がリラックスできず、歯を強く噛み締めたり、こすり合わせたりすると考えられています。
仕事や人間関係、家庭での悩みなど、心身に負担がかかっていると感じる場合は、ストレスが原因である可能性が高いでしょう。
噛み合わせの不調和
歯並びが悪く、噛み合わせがずれていることも、歯ぎしりの原因の一つです。特定の歯に過剰な負担がかかるような噛み合わせは、無意識のうちにその負担を軽減しようとして、歯ぎしりを引き起こすことがあります。
また、詰め物や被せ物の高さが合っていない場合も、噛み合わせの不調和を招き、歯ぎしりの原因となることがあります。矯正中の方の場合、歯が動く過程で噛み合わせが変化するため、一時的に歯ぎしりが起こりやすくなることもあります。
生活習慣
アルコールの摂取や喫煙も歯ぎしりの原因となることがあります。
アルコールには筋肉をリラックスさせる作用がありますが、過剰に摂取すると、かえって睡眠中の筋肉の緊張を高め、歯ぎしりを引き起こす可能性があります。また、タバコに含まれるニコチンは、交感神経を刺激するため、歯ぎしりの頻度を高めることが知られています。
さらに、カフェインの過剰摂取や激しい運動後の就寝なども、睡眠の質を低下させ、歯ぎしりを誘発する要因となり得ます。
マウスピース矯正中に歯ぎしりをするリスク

マウスピース矯正中に歯ぎしりをすると、矯正治療そのものに悪影響を及ぼすだけでなく、さまざまなリスクを伴います。ここでは、具体的なリスクについて詳しく解説します。
マウスピースが破損、変形する
マウスピースは、歯に矯正力をかけるために適切な厚みと硬さで設計されています。
しかし、歯ぎしりによる強い力が加わると、マウスピースにひびが入ったり、穴が開いたりすることがあります。特に、クレンチングのように強く噛み締めるタイプの歯ぎしりは、マウスピースに大きな負担をかけます。
マウスピースが変形したり破損したりすると、設計された矯正力がかからなくなり、矯正効果が低下することがあります。その結果、新しいマウスピースを作り直す必要が出てくると、その分の費用や時間が余計にかかることも考えられます。
歯や歯周組織への負担が増加する
矯正中の歯は動いている最中であり、歯根や歯周組織が通常よりも敏感な状態です。歯ぎしりによる強い力が加わると、歯根膜や顎関節に炎症を引き起こす可能性があります。
また、マウスピースを装着して歯ぎしりをすると、歯とマウスピースが一体となって、歯や顎に強い衝撃が加わります。これにより、歯の表面が削れたり、ひびが入ったりするリスクが高まります。
治療期間が延長する
歯ぎしりによってマウスピースが破損したり矯正効果が低下したりすると、治療計画の見直しが必要となります。計画の遅れを取り戻すために、追加でマウスピースを作製したり、治療期間を延長したりすることになると、当初の予定よりも治療期間が長引く可能性があります。
マウスピース矯正中の歯ぎしり対策

マウスピース矯正中の歯ぎしりは、矯正治療を成功させる上で大きな障害となり得ます。
しかし、いくつかの対策を講じることで、リスクを最小限に抑えられます。
ストレスを軽減する
歯ぎしりの主な原因の一つであるストレスを管理することが重要です。日中に適度な運動を取り入れたり、趣味の時間を設けたりして、リフレッシュできる環境を整えましょう。アロマテラピーや入浴など、リラックス効果のある方法を試してみるのも良いでしょう。
睡眠環境を整える
質の良い睡眠は歯ぎしり予防の基本です。睡眠環境を整えることで、歯ぎしりのリスクを軽減できます。
マットレスや枕の選択も重要です。自分の体型や寝姿勢に適したものを選ぶことで、身体の緊張を和らげ、リラックスした状態で眠れます。首や肩に負担がかからない高さの枕を使用し、背骨の自然なカーブを維持できるマットレスを選びましょう。
また、寝る前にスマホやパソコンを見るのを控え、ゆったりと過ごす時間を確保することで、睡眠の質を高められます。
歯科医院での相談とマウスピース調整
マウスピース矯正中の歯ぎしりについては、必ず担当の歯科医師に相談しましょう。患者さまの状態を総合的に評価し、対策を提案することができます。歯ぎしりの程度や頻度、マウスピースへの影響などを定期的にチェックしてもらいましょう。
マウスピースの調整も重要な対策の一つで、噛み合わせの微調整を行うことで、歯ぎしりの軽減が期待できる場合があります。また、マウスピースの材質や厚みを変更することで、破損のリスクを軽減できるケースもあります。
まとめ
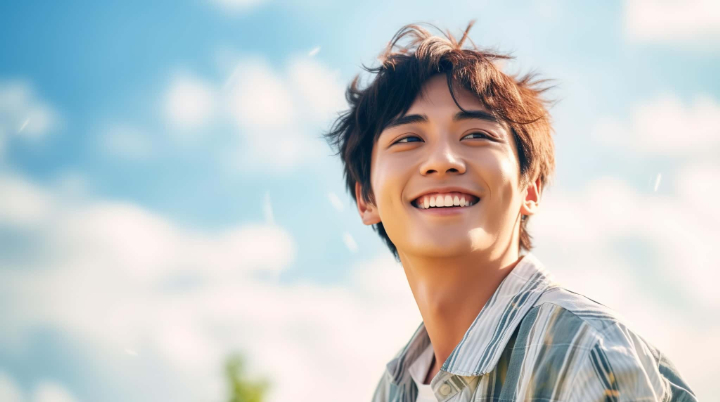
マウスピース矯正中の歯ぎしりは、マウスピースの破損や矯正効果の低下、顎関節への悪影響など、さまざまなリスクを伴います。
しかし、歯ぎしりの原因を理解し、適切な対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑え、矯正治療をスムーズに進められます。マウスピース矯正中に歯ぎしりが気になったり、マウスピースが破損した場合は、自己判断せずすぐに歯科医師に相談することが重要です。
マウスピース矯正を検討されている方は、千葉県野田市にある歯医者「R歯科・矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、インプラント治療やマウスピース矯正(インビザライン)、小児歯科、ホワイトニングなど、さまざまな治療に力を入れています。ホームページはこちら、Web診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。