歯周病の主な治療法と治療の流れ!進行を防ぐためのケア方法も
こんにちは。千葉県野田市にある歯医者「R歯科・矯正歯科クリニック」です。
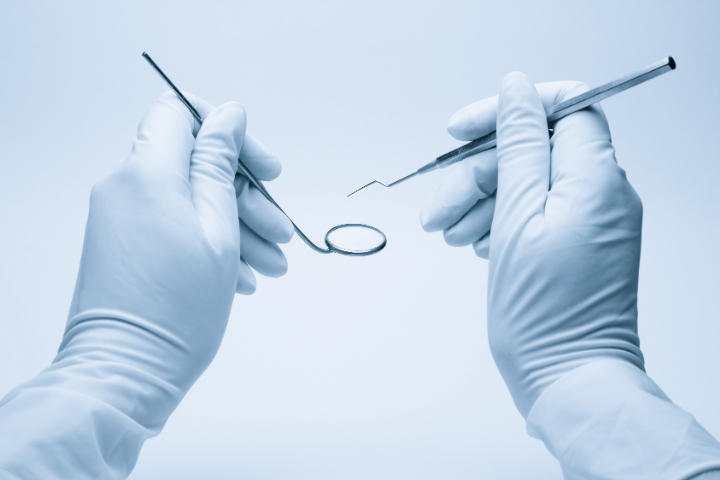
歯ぐきの腫れや出血、口臭が気になるといった症状がある場合、それは歯周病の兆候である可能性があります。初期段階では異変に気づきにくいものの、進行すると歯を支える骨にまでダメージが及び、やがて歯を失うリスクが高まる深刻な病気です。
しかし、早期に発見し、適切な治療と日々のケアを行うことで、進行を食い止められます。
この記事では、歯周病の基本的な治療法や治療の進め方、そして再発や悪化を防ぐために日常生活で意識すべきケア方法について、わかりやすく解説します。
歯周病の進行段階と症状

歯周病は、歯を支える組織に炎症が起こることで始まり、進行するにつれて歯を失うリスクが高まる病気です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに悪化しているケースも珍しくありません。
ここでは、歯周病の進行段階ごとの特徴と、それぞれに見られる症状について解説します。
歯肉炎
歯周病の初期段階である歯肉炎は、歯と歯ぐきの間にプラーク(歯垢)が溜まり、歯ぐきに炎症が起きる状態です。この段階では歯を支える骨に影響は及んでおらず、適切なケアを行えば改善が期待できます。
代表的な症状としては、歯ぐきの赤みや腫れ、歯みがき時の出血などが挙げられます。痛みを伴わないことも多く、見過ごされがちです。
軽度歯周炎
歯肉炎が進行すると、歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットが深くなり、細菌が内部に侵入しやすくなります。これにより歯槽骨(しそうこつ)という歯を支える骨が徐々に吸収され始め、歯ぐきの炎症もより顕著になります。
軽度の段階では、歯のぐらつきはあまり感じられませんが、歯ぐきの腫れや出血が続く、口臭が気になるなどの変化が現れます。
中等度歯周炎
中等度まで進行すると、歯槽骨の吸収がさらに進み、歯の支えが弱くなってきます。この段階では、歯ぐきが下がって歯が長く見える、食べ物が詰まりやすくなる、冷たいものがしみるといった症状が出てくることがあります。
歯のぐらつきも少しずつ自覚され始め、噛みにくさを感じることもあります。
重度歯周炎
歯周病が重度にまで進行すると、歯槽骨の大部分が失われ、歯はわずかな支えしかない状態になります。このため、歯が大きく動揺し、噛む力を保つことが難しくなります。強い口臭や持続的な膿の排出、明らかな痛みなども見られることがあります。
放置すると自然脱落することもあり、歯の保存が困難になるケースも多いです。
歯周病の治療法

歯周病は自然に治ることはなく、進行を食い止めるには適切な治療が欠かせません。進行の程度によって治療内容は異なりますが、基本的には原因となるプラークや歯石を取り除き、歯周組織の健康を回復させることが目的です。
ここでは、歯周病に対して行われる代表的な治療法について段階的に解説します。
プラークコントロールとブラッシング指導
歯周病治療の第一歩は、口腔内の環境を清潔に保つことです。歯科医師や歯科衛生士から、正しい歯の磨き方やケアの方法について指導を受けることで、日常のブラッシング効果が高まり、再発予防にもつながります。
特に、歯周ポケット内の汚れはセルフケアだけでは取り切れないため、専門的な清掃と併せて行うことが重要です。
スケーリングとルートプレーニング
歯周病の原因となる歯石やプラークは、歯と歯ぐきの間に深く入り込んでいることがあります。スケーリングでは、専用の器具を用いて歯面や歯周ポケット内の歯石を取り除きます。その後、ルートプレーニングによって歯根の表面をなめらかに整え、細菌の再付着を防ぎます。
これにより、炎症の軽減と歯ぐきの回復が期待できます。
歯周外科治療
歯周病が中度から重度に進行している場合、自宅でのブラッシングや通常のケアだけでは十分な改善が見込めないケースもあります。その場合、歯ぐきを切開して深部の歯石や感染組織を除去するフラップ手術などの歯周外科治療を検討します。
また、歯を支える骨が大きく失われている場合には、再生療法を併用するもあります。これにより、歯の保存や噛み合わせの改善を図ります。
噛み合わせの調整
歯周病が進行すると、歯の動揺が強くなり、噛み合わせに負担がかかることがあります。こうした状態を放置すると、さらに歯を支える組織が傷みやすくなるため、必要に応じて噛み合わせの調整を行います。
咬合調整では、わずかな歯の高さや接触のバランスを調整すれば、歯や歯ぐきへの過剰な力を和らげることが目的です。
メンテナンス(定期的な管理)
治療が終了した後も、歯周病は再発のリスクがある病気です。そのため、再発を防ぐには定期的な通院によるプロフェッショナルケアと、自宅での丁寧なセルフケアの継続が不可欠です。
歯科医院では、歯周ポケットの深さの確認やプラークの付着状況をチェックし、必要に応じて清掃や指導を行います。
歯周病治療の流れ

以下に、一般的な歯周病治療の流れについてご紹介します。
<歯周病治療の流れ>
| 治療ステップ | 内容 | 目的・ポイント |
|---|---|---|
| 初診・検査 | 視診・歯周ポケット測定・レントゲン検査などを実施 | 歯周病の進行度や骨の状態を把握し、治療計画を立てる |
| 動機づけとセルフケア指導 | 歯周病の現状説明 歯みがき指導 生活習慣のアドバイス | 患者さま自身の理解とセルフケアの習慣づけ |
| スケーリング・ルートプレーニング | 専門的な器具で歯石・プラーク除去 歯根表面を滑らかに整える | 歯ぐきの炎症を抑え、細菌の再付着を防ぐ |
| 再評価と経過観察 | 再検査により歯周ポケットの深さや改善度を確認 | 初期治療の効果を評価し、必要に応じて追加治療を判断 |
| 歯周外科治療(必要な場合) | フラップ手術、再生療法などの外科的処置を実施 | 重度の歯周病に対し、深い部分の清掃や組織再生を図る |
| メンテナンスと予防管理 | 定期検診 クリーニング セルフケアの継続 | 再発を防ぎ、歯周組織の健康を長期的に維持する |
歯周病の進行を防ぐために自宅でできるケア

歯周病は進行してからの治療よりも、日々のケアによる予防や早期対策が非常に重要です。歯科医院での定期的なメンテナンスと並行して、自宅でも正しいセルフケアを継続することで、歯ぐきの健康を守れます。
ここでは、歯周病の予防と進行抑制につながる、自宅で取り組めるケア方法について詳しく解説します。
正しいブラッシングを習慣づける
歯周病予防の基本は、やはり毎日の丁寧なブラッシングです。特に、歯と歯ぐきの境目にプラークが残りやすいため、歯ブラシの毛先を歯ぐきに軽く当てて、小刻みに動かしながら磨くことが重要です。
力を入れすぎると歯ぐきを傷つける恐れがあるため、やさしく磨くよう心がけましょう。時間をかけて全体を磨くことが、プラークの取り残しを防ぐポイントです。
デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
歯ブラシだけでは、歯と歯の間に溜まる汚れを完全に取り除くのは難しい場合があります。そこで役立つのが、デンタルフロスや歯間ブラシといった補助清掃用具です。これらを併用することで、見えにくい部分のプラークや食べかすを除去しやすくなります。
特に、歯周病の予防では、こうした細部のケアが大きな差につながります。
殺菌効果のある洗口液を活用する
歯磨き後に洗口液を使用することで、口腔内の細菌の増殖を抑える効果が期待できます。市販されている洗口液の中には、歯周病予防に特化した成分を含んだものもあります。
ただし、洗口液だけではプラーク除去は不十分なので、あくまでブラッシングの補助として活用するのが適切です。
食生活を見直す
歯周病の予防には、栄養バランスの取れた食事も欠かせません。特にビタミンCやカルシウム、たんぱく質などは、歯や歯ぐきの健康維持に役立ちます。
反対に、糖分の多い食品や間食の頻度が高いと、口腔内の細菌が活発になりやすくなるため、食生活を整えることも大切なケアの一つといえるでしょう。
ストレスや喫煙の影響を見直す
ストレスが溜まると免疫力が低下し、歯周病の進行を助長することがあります。また、喫煙は歯ぐきの血流を悪化させるため、歯周組織の修復が遅れやすくなります。
こうした生活習慣の見直しも、歯ぐきの健康を守るうえで欠かせない要素です。禁煙を含めた生活環境の改善は、長期的に見て歯の寿命を延ばすことにもつながります。
まとめ

歯周病は自覚しづらいまま進行することが多く、早い段階では症状に気づきにくい点が特徴です。
しかし、早期に発見し適切な治療を受けることで、歯ぐきの健康を守り、将来的な歯の喪失を防げます。治療は症状の進行度に応じて異なり、歯石除去や外科的処置が必要となる場合もありますが、どの段階でも日々のセルフケアと歯科医院での継続的な管理が欠かせません。
違和感を覚えたら放置せず、早めに歯科医師に相談しましょう。毎日のケアと定期検診が、健やかな口腔環境を保つための第一歩です。
歯周病の治療を検討されている方は、千葉県野田市にある歯医者「R歯科・矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、インプラント治療やマウスピース矯正(インビザライン)、小児歯科、ホワイトニングなど、さまざまな治療に力を入れています。ホームページはこちら、Web診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。